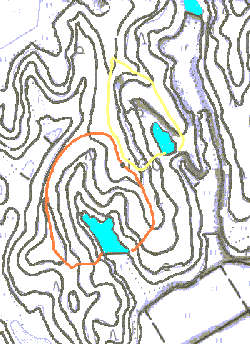 |
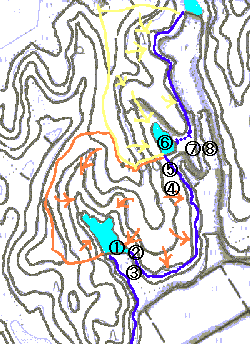 |
明石川流域の溜池
神戸市内の明石川の流域は、旧くは播磨の国、瀬戸内地方に位置します。
瀬戸内海沿岸は有数の少雨地帯で、年間降水量はおよそ1,200mm。全国平均の6割程度です。
灌漑に適した河川が無い地域には、少ない天水を有効に利用するため溜池が数多く築かれています。
讃岐平野や印南台地です。
その印南台地の足元に、明石川は位置しています。
更に、明石川流域は傾動する六甲山塊の裏面に位置するため、
上昇する土地は川に侵食され、両岸に残された土地は段丘となります。
狭い階段状の段丘面は、川から遠く水の少ない土地です。
段丘の斜面に刻み込まれた支谷の谷頭には、例外なく溜池が造られています。
明石川流域の田んぼをジョグしてまわるうちに、 水も漏らさぬ溜池の集水システムの存在を知りました。
溜池の集水方法
それでは、ここに溜池の仕組みを紹介しましょう。
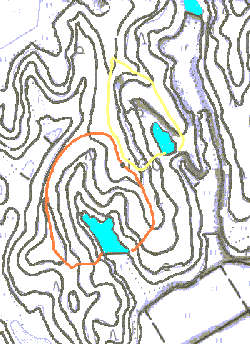 |
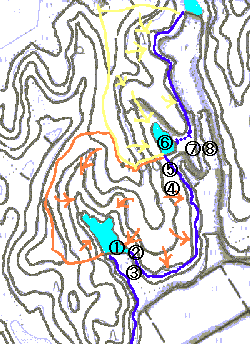 |
まず、左側の地図をご覧ください。
何もしていなければ、溜池に流れ込むのは、その池の上流にある斜面に降る雨水です。
ところが、実際には右の図のように、池から池へ雑木林の中を、等高線に沿った水路が走っています。
普段は空の水路ですが、雨が降ると下流の(左側の)池へ雨水を流します。
この水路のおかげで、溜池の流域はおよそ二倍に広がることになります。
図の中の番号は下の写真の撮影位置です。

① 野鳥の姿を追ってたどりついた |

② 堰堤の右手奥に、 |

③ 流れ込み口のパイプは、すぐに |

④ 丘の端を回りこんだ水路は、 |

⑤ 水路をたどると、その先には |

⑥ 上の溜池(ねずみ谷池)は少し小さく、 |

⑦ 上の池の堰堤右側にトンネルがありました。 |

⑧ 中を覗くと素掘りの穴の向こうに光が見えます。 |
10m程度の堰堤の高さから考えると、 これらの溜池は戦後か、精々昭和初期に再築されたもののように思います。 その後、堰堤はよく手入れされているようですが、 残念ながら水路は所々で崩れたり埋もれたりしています。
林崎疏水
つぎに、明石川の流域で最も名高い林崎疏水を紹介します。
この用水は、明石川右岸の林、和坂、松江東、松枝西、藤江、鳥羽の村々へ水を送るため、 江戸時代初期の1657年から68年に作られたものです。 流末にある溜池、野々池の池頭の記念碑や説明板に、その略歴が記されています。
現在の林崎疏水は、明石川の中流、西戸田の可動堰で取水し、中流の田畑の間を抜け、
段丘のふもとをとおり第2神明をくぐったあと、台地の掘割を抜けて野々池に至ります。
その全長は5,347mとありました。疏水管理用の通路が水路沿いに設けられています。
ある日、その管理通路を走ってみました。
全延長のうち、まだまだ素掘りの古い水路が残っています。
台地のふもとに作られたその水路の構造は、このあたりの溜池の導水路に似ています。
林崎疏水は、最初は明石川の水を、こうした溜池の導水路を連ねて引いたのではないでしょうか?
そして最後に台地の掘割を掘削したのかもしれません。
工期一年間で完成したとすると、こういった工法をとったのかもしれません。
疏水の位置図 |
1. 中湧井堰 |
2. 疏水はここから始まります。 |
3. 水路は田んぼの中を流れます。 |
4. 疏水は農地の排水路を越えて流れます。 |
5. 福知川堤防から北を望む。 |
6. 福知川を伏越で越えます。 |
7. 福知川の川床。 |
8. 農家の前を流れる水路。 |
9. 家庭の用水としても疎水を利用したようです。 |
10. 疎水は第二神明道路の下をくぐります。 |
11. コンクリート三面張水路もありますが、 |
12. 丘の麓を利用した、立派な堤防です。 |
13. 水路の周りには、竹林がたくさんあります。 |
14. 出合の大池の上のあたり。 |
15. 疏水の最後にある掘割。 |
16. 水路沿いにキリの木が何本かありました。 |
17. 掘割を抜けた疏水は溜池に分水されます。 |
18. 林崎疏水建設の記念碑。 |
19. 疏水はここで、それぞれの溜池へ分水されます。 |
20. 最も大きな野々池は明石市の水源池となっています。 |
21. まだ農業用水に使っている池もあります。 |
ここをクリックすると、ページトップへ戻る